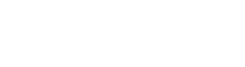ヤマハ発動機株式会社
ヤマハ発動機がオウンドメディアをつくったワケ(後編)──モノではなくコトを伝えるソーシャルコミュニケーション
クライアント課題
- 若年層のブランド認知低下
- 自社アセットの蓄積
- 点ではなく面でのターゲットコミュニケーション
ADDIXの創造
- ブランドと若年層のタッチポイントの設計
- コンテンツを発信・蓄積できる場
- ターゲットインサイトに寄り添ったクリエイティブ
プラットフォームに依存しないユーザーコミュニケーション
前編にてヤマハ発動機初のオウンドメディアについて、立ち上げ時のストーリーやコンセプトについてお聞きしました。Instagramではどんなことを行っていますか?
「HATSUDO」という箱ができて、そこから日常にあふれるさまざまなトキメキを発信・蓄積していますが、ただ発信しているだけでは見ていただくことはできません。だから、若年層とのタッチポイントとしてInstagramを運用し、コンテンツを発信しています。

ヤマハ発動機株式会社 企画・財務本部 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ 主務 小野寺廉さん
ヤマハ発動機では他にもいくつかのInstagramアカウントを運用していますが、バイクなど既存製品のファン以外の若年層にもリーチさせたかったんです。
既存ファンを置いていくことはありませんし、これまでやってきた取り組みが悪かったということもありません。ただ、ヤマハ発動機をまだ知らない、あるいは知っていても深く理解していない若年層とコミュニケーションをするわけですから、これまでと違ったアプローチが必要でした。ですから、彼らに響くクリエイティブにもこだわっています。

ヤマハ発動機株式会社 企画・財務本部 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ マネージャー 岩崎慎さん
私がプロジェクトに参加したのは、お取り引き決定後からでしたが、これまで議論してきた「“トキメキ”が発動する瞬間を伝える」というコンセプトを、Instagramでどのように伝えていけばいいのか。ターゲットである若年層に見てもらい、そのうえで受け入れてもらえるかを常に考えています。

そうした観点で、メディア運営の知見に加え、意思疎通のできるデザイナーと連携できることはとても大きいですね。SNS運用を切り離して考えるのではなく、オウンドメディアと若年層をつなぐ手段としてSNSを考え、トータルでクリエイティブをつくれるのがADDIXの強みのひとつだと思います。
デザイン力の高さはコンペから認識していましたが、その後いろいろな議論を重ねていくたびに、どんどんブラッシュアップされていったイメージです。
クライアント×制作チーム。異なる視点をいかに紡いでいくか
メディア運営や雑誌制作の経験から培われたADDIXのデザイン力。クライアントと制作チーム間の認識合わせはどのように行っていたのでしょうか?
デザインについて、こちらから具体的なオーダーを出したことはありません。でも、最初のデザインを見たときから「おお!」と思いましたよ。
ありがとうございます。コンペの段階から「トキメキ」というコンセプトが軸にあり、まずはそれをどう表現するか?から考えて、ロゴやサイトデザインに落としていきました。

たとえば、「トキメキって何だろう?どういうこと?」と考えたときに、“ドキッ”とする感覚だったり、“キラッ”としたイメージが湧いたりしたので、それをデザインに取り入れてみる。もうちょっと内面に意識を向けてみると、“体温が上がる”ような感覚になるんじゃないかなと思ったので、温かみを感じる色を採用して、ページに動きをつけてみたり、などですね。
私自身もかわいい!と思うデザインですね。そして、そんなサイトデザインを踏襲しながら、Instagramのクリエイティブも合わせてつくってくれる。運用するメンバーとしても気持ちが上がります。

そう言ってもらえるとうれしいですね。ターゲットに合わせることは大前提ですが、同じ若年層に向けたデザインでも、広く受け入れられる方向か、あるいは尖らせる方向かは悩んだんです。でも、トキメキというワクワクするようなオウンドメディアだから「ちょっと変わっていてもいいのでは?」と、世界観を守りつつも変化を楽しめるようなデザインを心がけました。
改めて考えると、ヤマハ発動機さんに自由にやらせていただくことができたからですね。クライアントワークでここまでお任せしていただけるケースは稀なので、デザイナーとして実はすごく有難いことだと感じています。
もちろん意思や希望はあるんですけど、ヤマハ発動機としての考えをバイアスにしてほしくなかったんです。これは広報グループだけでなく、ヤマハ発動機自体がそうした企業風土なのかもしれませんが。いずれにしても、そこであれこれ口を出してしまったら、プロにお任せする意味がないですから。
同じチームとしてチャレンジしていきたいし、してほしい。失敗は起こるものだから、それを責めたりはしませんね。ただ、チャレンジを辞めたり、アクションを止めたりすることはしてほしくないです。

そういった姿勢でいていただけるからこそ、私たちも「もっとできることはないか?」と常に考えられるし、同じ目線でクリエイティブをつくることができるのだと思います。もちろん、ときには「ちょっと違うのでは?」といった意見もいただきますが、正直に議論し合えるから、「じゃあこれでやってみよう」とか「ここは変えよう」といった判断にしっかり着地できますし、次のアクションにもつなげやすいですね。
見える数字と見えない数字を探求するためのPDCA
立ち上げから1年でフォロワー4,000人を突破。KPIやPDCAサイクルはどのように設計していますか?
手探り状態の立ち上げ時に掲げたKPIは、3年間でフォロワー8万人達成というものでした。これは既存のヤマハ発動機アカウントのフォロワーに由来していて、ひとつのベンチマークとして掲げたものです。
しかし、実際にオウンドメディアを立ち上げて運用してみると、なかなかハードルが高いということがわかってきましたね。
ヤマハ発動機さまからのオーダーのひとつに、「数字に縛られすぎないでほしい」というのがありました。プロジェクトにおいて数字を追うことは当然ですが、フォロワー数を重視するあまり本質を見失ってしまうことも多々あります。ですが、「HATSUDO」には若年層とのコミュニケーションを大事にしたい、ちゃんとファンになってほしいという想いがしっかりあるので、KPIとしてアカウントの成果を示すフォロワー数はもちろん大事にしつつ、目に見える数字だけでない「フォロワーの質」もしっかり見ていくようにしています。
では何を見るか?というといくつかあるのですが、ひとつはエンゲージメント率です。あくまでアカウントの性質を第一としながら、トレンドに縛られ過ぎないバランスで、しっかりと定着してくれるフォロワーを獲得するためにコンテンツのPDCAを頻繁に回しています。

あと、広告とのバランスも大事ですね。HATSUDOをより多くの人に知っていただくために継続的に広告配信をしていますが、広告で獲得したフォロワーは定着しにくく、いつのまにかフォローを外していたり、フォローしていても投稿を見ていなかったりすることも多いです。そうした目に見えない部分にもフォーカスし、新規フォロワーと投稿コンテンツのマッチングを日々行うようにしています。
Instagramの知見に乏しい僕らにとってはとてもありがたいです。月次レポートも詳細に出してくれますし、そこから次にどんなアクションをしていくかなど、分析から提案までしてくれますしね。
メディアもSNSもそうですが、企業感を感じてしまうとユーザーは近づきませんし、来たと思ってもすぐ離れてしまいます。フィード投稿などの素材も、中村たちが企画・構成したものを私のほうでデザインしているのですが、なるべく親しみを感じてもらえるような、トキメキを感じてもらえるようなものを意識しています。
こうした部分も、たとえばABテストのような「赤か青か」の判断だけではできないクリエイティブのこだわりかなと思います。

むずかしいのは、「HATSUDO」はいわゆる情報発信型のアカウントではないので、フォロワー数が伸びづらい性質であること。だから、目を止めるインパクトは演出しつつも、ユーザーにとってわかりやすいテキストや構成を意識して、常に改善を繰り返しています。一方で、リールやカルーセルコンテンツなど取り入れやすいものも積極的にチャレンジして、フォロワーに響くコンテンツを見出せるようになってきました。
ここ最近でとくにエンゲージメント率がよかったものに、「香りのトキメキ」というコンテンツがありました。著名人やスタッフなどいろいろな人から香りに関するトキメキを集め、それをカルーセル投稿したのですが、高エンゲージメント率で保存数も多く、フォロワー獲得にも貢献しました。
さらなる活性化に向けてこれからもチャレンジしていく
チャレンジの末にさまざまな可能性を見出してきた1年間。次の1年をどのように運用していきたいですか?
「HATSUDO」を通じて若年層とコミュニケーションするなかで改めてわかったのは、1,000人いたら1,000通りのトキメキがあるということ。色もかたちも温度もちがうトキメキが、ちゃんとあるんですね。
でも、それを扱っているメディアって実はあまりない。「HATSUDO」は今後もそこにフォーカスして、ユーザーを巻き込みながら、お互いのトキメキを「いいよね」って言い合える場にできたらなと思います。

つくり手や発信する側も、いちファンとして楽しんでいるべきですよね。「HATSUDO」を知ってほしい、楽しんでほしいと思う僕ら自身が、まず一番のファンでいなければいけないと。こういうのってお金の関係だけでは築けなくて、そういう意味ではいっしょに楽しみながらつくっていけるこのチームだからいいんでしょう。
そして、僕らが発信する「いいよね」をキッカケとして、それぞれのトキメキに気付いてくれたらうれしいですね。

Webでも雑誌でも、楽しんでいるかどうかって本当に出ますよね。私は、このメディアやInstagramをデザインするのが楽しいです。
楽しむという意味では、音声メディアをやってみたいですね。これまでもさまざまなトキメキを紹介してきましたが、もっと多くの人のいろんなトキメキを深掘ってみたいなと。

ここでは言い切れないくらいやってみたいことはありますが…(笑)この1年で土台はできたと思うので、引き続きアカウント第一をキープしながら柔軟かつクイックにチャレンジを続けていきたいです。音声メディアもいいし、リアルユーザーを巻き込んだイベントももっとやってみたいですね。

2024年末、ヤマハ発動機が運営する「YAMAHA e-RIDE BASE」とのコラボレーションで、HATSUDO初のリアルイベントを開催。今後もさまざまな取り組みにチャレンジしていく。
「新しいことをやってみようかな」という発見に出合えたり、「何かあるかも?」と期待してもらえたりするアカウントに育ってくれるようこれからもがんばります。

ヤマハ発動機株式会社について
静岡県磐田市に本拠を構え、パワートレイン技術、車体艇体技術、制御技術、生産技術を核としながら、二輪車や電動アシスト自転車などのランドモビリティ事業、ボートや船外機等のマリン事業、半導体製造装置などのロボティクス事業、ファイナンス事業など多軸に事業展開。世界30ヶ国・地域のグループ140社を通じた開発・生産・販売活動を行い、企業目的である「感動創造企業」の実現に取り組む。